 みけねこ
みけねこ4才の子どもの力を伸ばしたい。家でどんなことができる?
この記事では、4才のお子さんの「育ち」と、家庭でできる関わり方を発達の専門家:言語聴覚士が解説します。


- 国家資格:言語聴覚士(ST)免許保有
- 総合病院で働く小児ST
- お子さんの発達を支援する仕事をしている
4才の「育ち」の概要
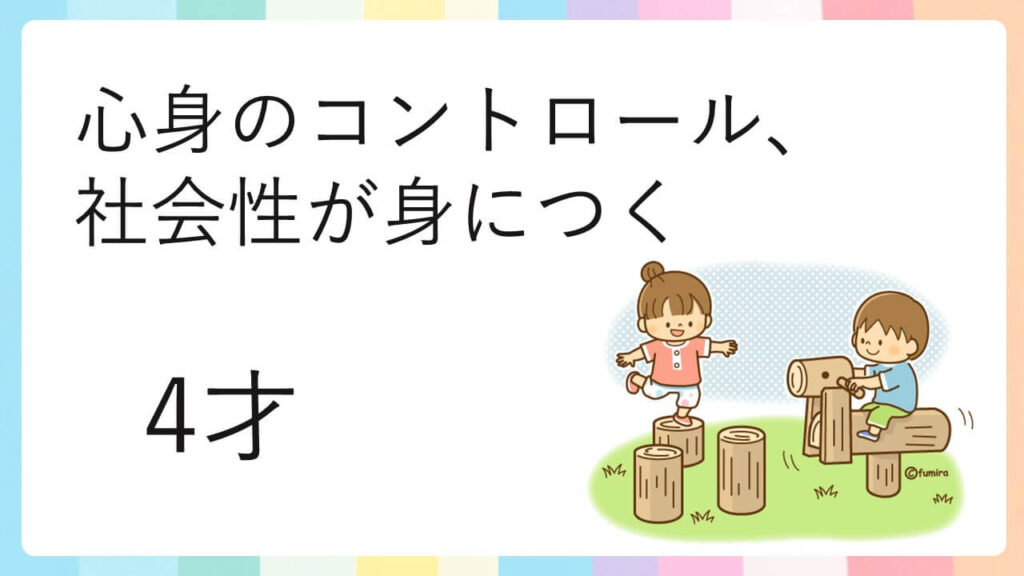
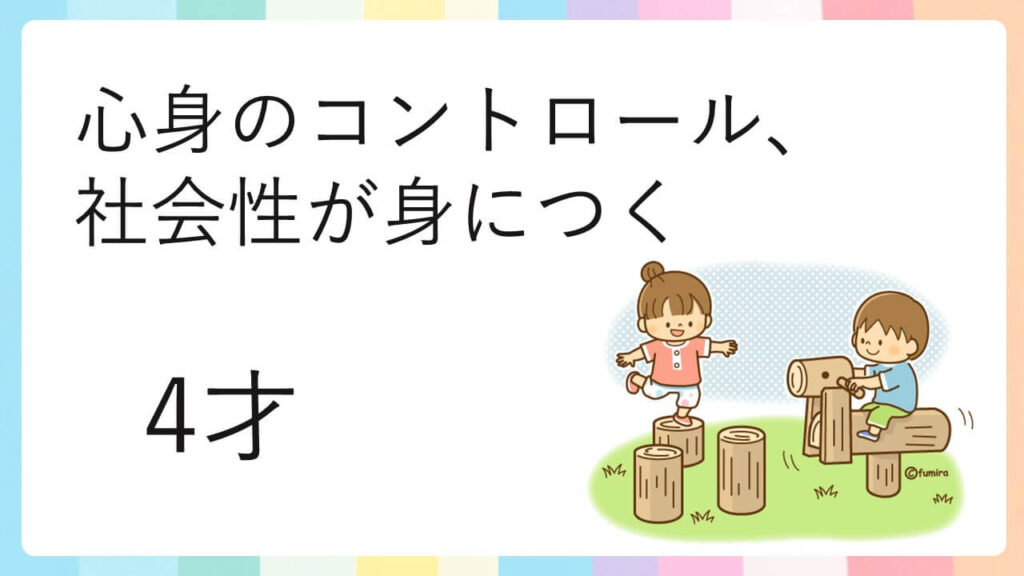
全身のバランスをとる力が発達し、身体の動きが巧みになる4才。
目的をもって、つくったり・描いたり・試したりする一方、想像力が豊かになり、失敗を予想して不安になるなどの葛藤もみられるのではないでしょうか。
身近な人の気持ちを察することができるようになるので、少しずつ「がまんする力」も育ってきます。
そんな4才のお子さんの「育ち」と「おうちでできる関わり」について、以下の内容について解説します。
- 全身の運動
- 指の巧緻性
- ことば
- 概念の形成
- 衣類の着脱
1つずつみていきましょう。
4才の「全身の運動」


4歳は「~しながら~する」の時期です。
2つの別々の動作を「1つのまとめあげた動作」にすることができるようになります。
例えば
- 「手を水平に上げる」+「走る」→トンボの運動
- 「手を頭の上に上げて耳に」+「両足で飛ぶ」→ウサギの運動
「~しながら~する」を意識して、おうちで楽しみながらご両親と遊べるといいですね!
運動遊びの例をいくつか紹介します。
ボールを蹴る
「いち、にの、さん!」でボールを蹴る遊びです。
「蹴る」という動作に「タイミングを合わせて」をプラスしてみましょう。
その他、「弱く蹴る」、「強く蹴る」といったアレンジを加えてもよいですね。
キャッチボール
「タイミングよく」+「キャッチする」が目標です。
ボールは20cmくらいのゴム製のものを使用します。
- 転がしたボールを「キャッチ」
- バウンドさせたボールをキャッチ
- バウンドなしでキャッチ
の順番ですすめましょう。
また、4歳は「投げる」ことも一気に上手になります。
バウンドしてもよいので、子どもが楽しくできる距離で行うといいですね!



「右利き・左利き」もはっきり決まってくる時期だよ。
雑巾がけレース
「雑巾を床にあてる」+「前に進む」の動作です。
全身を使う動きなのでおススメです。
スタートとゴールを決めて「よーい、ドン」の合図で行いましょう。
競争を取り入れて、あくまで「遊び」として行いますよ。



競争では子どもが勝てるように調整しよう。
4才の「指先の巧緻性」


大きな運動の次は「指先の巧緻性」について解説します。
指先の巧緻性
指先の器用さのこと。鉛筆やハサミの使用につながっていく動作。その他、衣類の着脱、手洗い、歯磨きなどの生活に必要な活動の土台となる。
左右の手で違う動きをしながら行う活動ができる時期です。
- ハサミをチョキチョキ動かしながら、反対の手で紙を動かして曲線を切る
- 粘土を持ちながら、反対の手は竹ひごを使って細工する
などです。
指先の巧緻性を高める活動自体が、「ひらがなを書く」力につながっていきます。
そのための活動を紹介しますので参考にしてみてください。
姿勢も意識して
椅子に座って行う活動が多いですが、意外と大切なのが「姿勢」。
集中力にも影響します。
ハサミ
右手と左手が別の動きができるようになることで、紙を動かしながら切れるようになります。
そのための活動として
- 円形のもの
- ギザギザのもの
などを切る練習を取り入れてみてください。
はじめはうまくいかなくても少しずつ上手になっていきます。



手を切らないように気を付けてね。
鉛筆
お手本を見ながら描くことができるようになってきます。
この時期あたりから、人を描くと「胴体」も表現できるようになります。
この時期、まだ「ひらがな」を書けるお子さんは少ないと思います。
- 線引き
- なぞり書き
などで「運筆力」を高める関わりがよいでしょう。
粘土
ちぎったり、引っ張ったり、押し込んだりと、粘土は指先の力加減が育まれる活動です。
4才では、目的をもって作り「見立て遊び」までできることが目標です。
- ケーキ
- 植物
- 乗り物
- 動物など
を作るお子さんが多いですね。
難しい場合は、まずご両親が見本を作ってあげるとよいですよ。
ぞうきん絞り
ぞうきんを縦に持って、左右の手を逆方向に動かすことでぞうきんをねじります。
左右の手を逆方向に動かすことが意外と難しいです。
固く絞れるように、楽しい雰囲気で教えてあげてください。
そのまま、おそうじのお手伝いができれば◎ですね。
ボタン
ボタンの留め外しは指先の巧緻性が育まれつつ、自立心も高まるのでこの時期に教えたい活動です。
ボタンを留める動作は
- ボタンの側面が見えるように持つ
- ボタンの穴に合わせて側面から入れる
- 穴から出たボタンを指先で引っぱり出す
の3ステップで教えてあげましょう。
難しい場合は、鏡を見ながらボタンがどうなっているか確認してみると、うまく行く場合があります。



大きなボタンの方が簡単だよ。
4才の「ことば」


温かい雰囲気の中で、ご両親と会話を交わし、ことばのおもしろさを感じるように関わります。
また、「つぶやき語」も大切にします。
つぶやき語
この時期に「ひとり言(ひとりごと)」が増えることを不安に思うご両親もいるでしょう。
つぶやき語といわれる「ひとり言」は、「言葉」を用いて思考したり、言葉で行動をコントロールしたりすることが「できるようになった」証しです。
4才台の、ことばへの関心を高める関わりを3つ紹介します。
絵本・紙芝居
普段、大人が子どもに話しかける「言葉」は子どもが理解できるように簡単・わかりやすい言葉を使いがちです。
一方、絵本や紙芝居で出てくる言葉は、普段なかなか使わないフレーズが多く含まれています。
- ところが
- どうしてかというと
など耳にする機会の少ない言葉を覚える機会になります。
積極的に絵本の読み聞かせをしたいですね。



個人的に「絵本の読み聞かせ」は幼児期のことばの発達において、もっとも効果的かつ有効な手段だと思っています!
経験し、感じたことを言葉にする
当然ですが、理解できることしか話すことしかできません。
そのため、色々なことを経験し、感じるということはことばの発達において重要です。
- ざらざらしている
- ヌルヌルしている
子どもが感じていることを、実況中継するようにご両親が言葉にして話しかけます。
ポイント
ご両親がよく言うフレーズは、子どもも使うようになります。
絵日記
絵日記は「語い」を増やす効果がかなり大きいです。
ポイント
絵と文字を書くのはご両親です。
一緒にでかけた場所を振り返りながら、ご両親が絵を描きます。
ご両親も知っている経験なので、「公園の滑り台は何色だったかな?」と正解を促すことができます。
過去の出来事について、「~だけど」「~だから」といった接続詞を使って説明できることが目標です。
- 「疲れたけど、頑張ったよね」
- 「日曜日だから、人が多かったよね」



会話を楽しみながら取り組むよ。
4才の「概念の形成」


「概念の形成」というと少し難しいですね。
「モノの特徴がわかる力」というニュアンスです。
「リンゴ、みかん、はさみ」の3つのうち「はさみ」が仲間はずれでだとわかるのは、「くだもの」という概念があるからです。
概念があると「共通認識」ができるので、コミュニケ―ションが効率的になります。
30cmのリンゴを見て「すごい!」で伝わるのは、一般的にリンゴは10cmくらいという「共通認識」があるからです。
「ことばの発達」にも影響する、「概念」の形成を育む関わりを紹介します。



ここでは「数」も概念に含めて説明するよ。
4歳は、物事を多面的に捉える力を育んでいきましょう。
「中くらい」を意識して
「大きい-小さい」という概念に加えて、「中くらい」という概念がわかるようになります。
そのために、
色々な大きさの積み木を小さい順で並べます。
「大・中・小」の3つよりも多くてもOKです。
「大きい」のよりも小さいけど、「小さい」のよりは大きい。
という概念に繋がります。



石や食べ物を使ってもいいね。
「~個」がわかるように
「~個」と言えるようになるために、ご両親が積極的に「~個あるね」と声かけします。
親「積み木何個ある?」
子「1、2、3、4、よん!」
親「そうだね、4個だね」
といった具合で正解をたくさん聞かせてあげます。



たくさん耳にする言葉は子どもも使うようになるからね。
「3個」が見てわかる
お店屋さんごっこも「数」の概念を身につける関りです。
4才は「数」について、少し丁寧に関わりましょう。
4才のお子さんは
- ひと目で見てわかるのは「3個」
- 「1個、2個、3個…」と言いながらならもう少し多い数
がわかります。
お店屋さんごっこでは、「ミカンを5つください」など、数えながら正しい数を選べるような関わりをしてみましょう。
4才の「衣類の着脱」
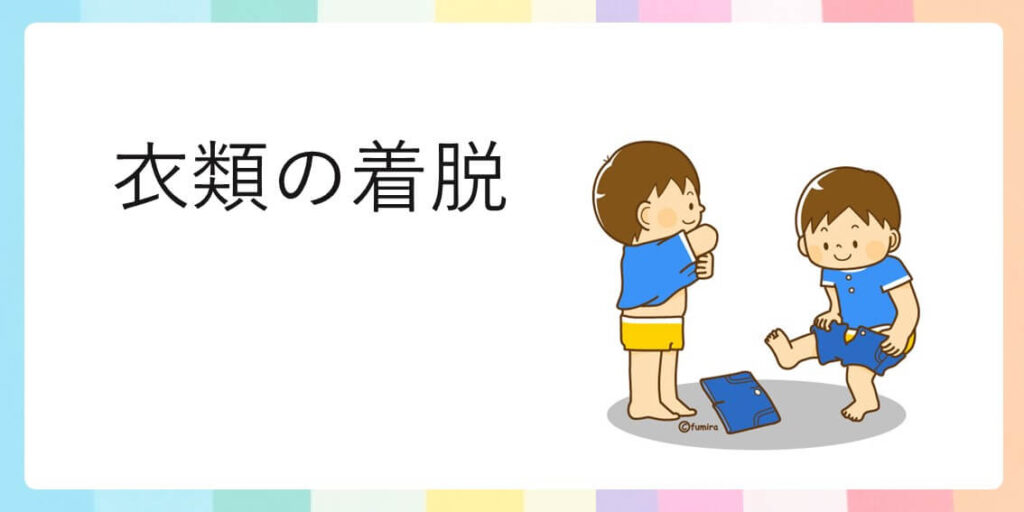
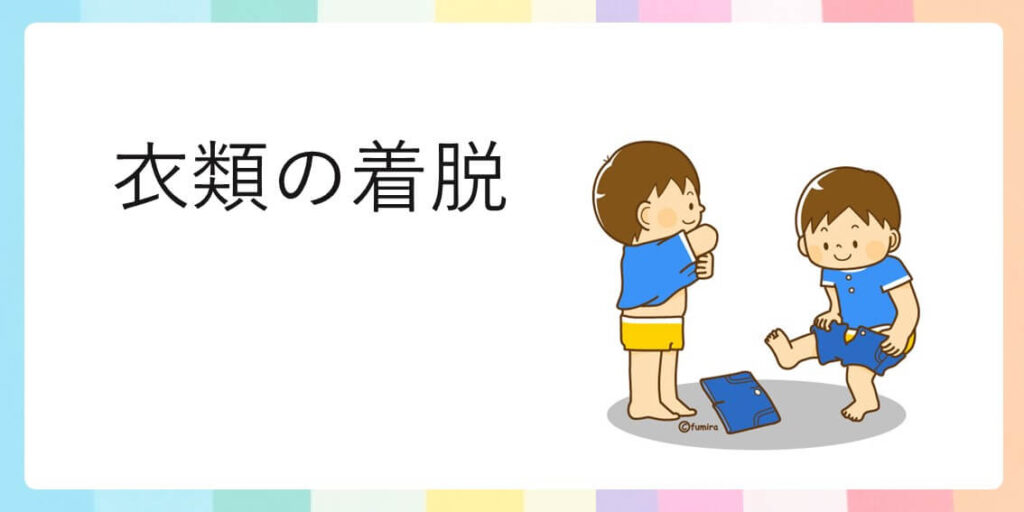
4才になると自分でお着替えができる服が多くなってきます。
手先も器用になり、目で見える場所のボタンも留めることができるようになってきます。
順序よく自分で身支度をする姿もみられるのではないでしょうか。
以下に4才台でできる「衣類の着脱」を挙げました。
4才台の「衣類の着脱」
- 靴の左右を意識して正しく履く
- 見えるボタンの留め外しができる
- 着ているものを全部脱ぐことができる
- シャツが出ていると自分で気づく
- 順序よく衣類の支度をする
ファスナーなど難しい動作は前半部分を手伝い、後半を子どもが行うとなどして手柄は渡してあげます。
また、前を上にした状態で広げて置いておくと、前後がわかりやすく着替えがしやすくなります。
まとめ
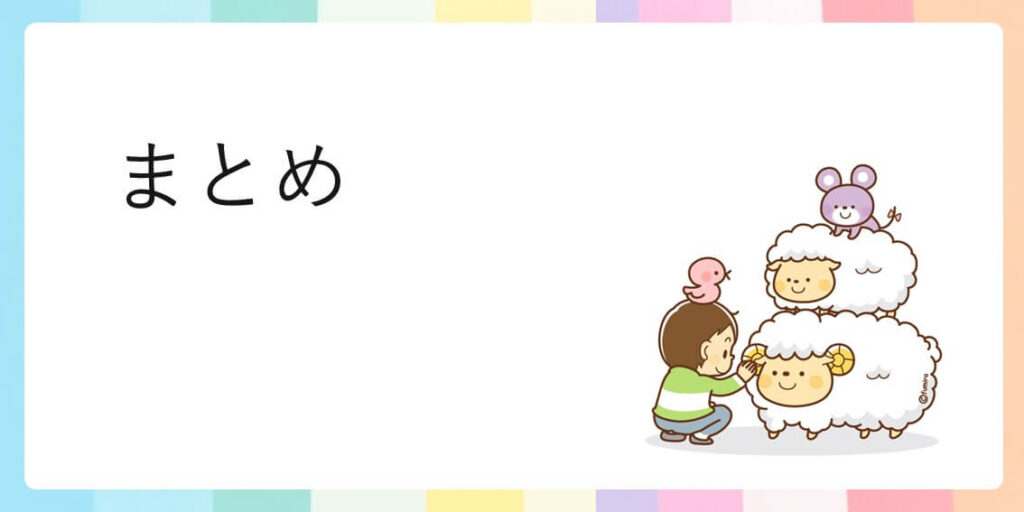
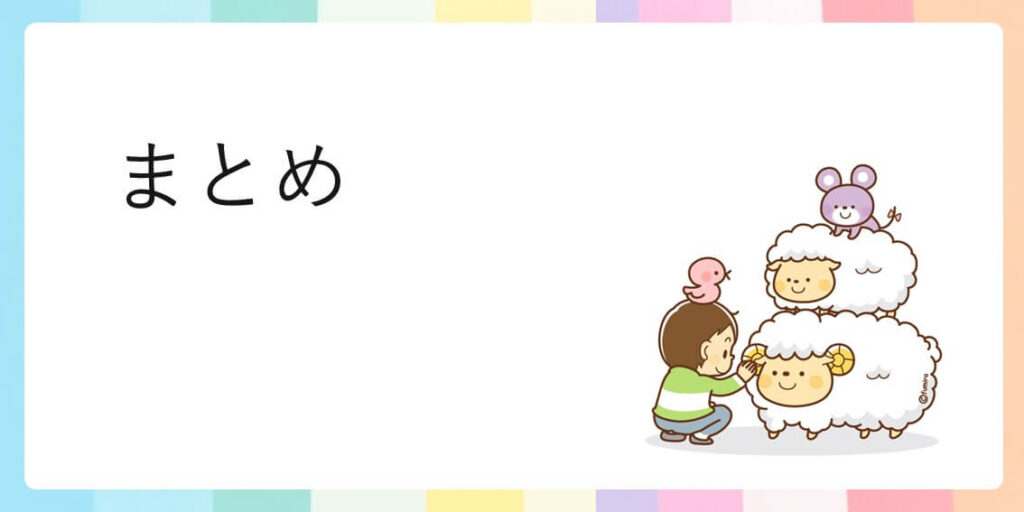
4歳のお子さんの学びと、家で取り組める関わりについて紹介しました。
おうちでできる取り組みの参考にしてくださいね。



最後までお読みいただきありがとうございました。




コメント