 みけねこ
みけねこ5才の子どもの力を伸ばしたい。家でどんなことができる?
この記事では、5才のお子さんの「育ち」と、家庭でできる関わり方を発達の専門家:言語聴覚士が解説します。


- 国家資格:言語聴覚士(ST)免許保有
- 総合病院で働く小児ST
- お子さんの発達を支援する仕事をしている
5才の「育ち」の概要
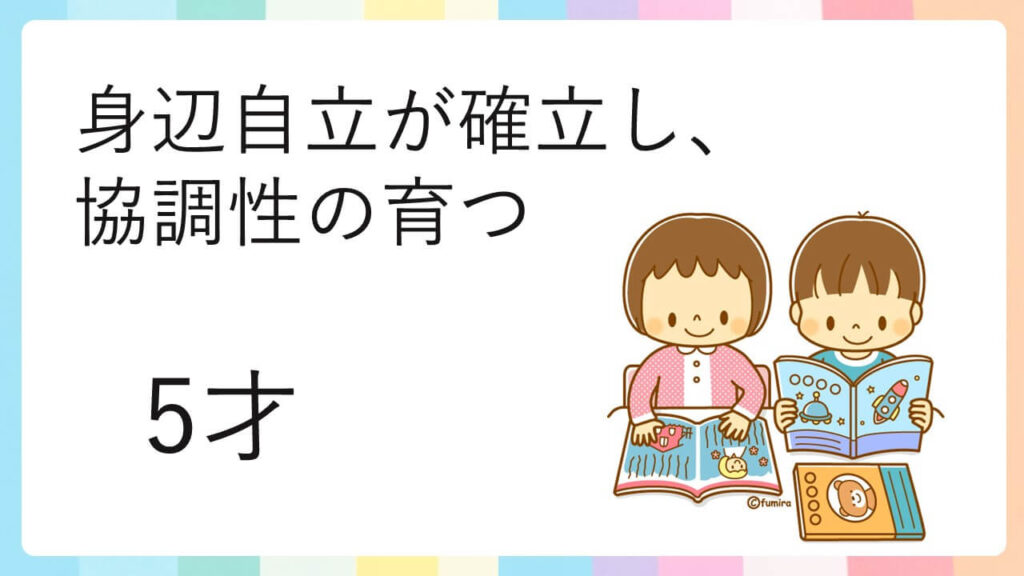
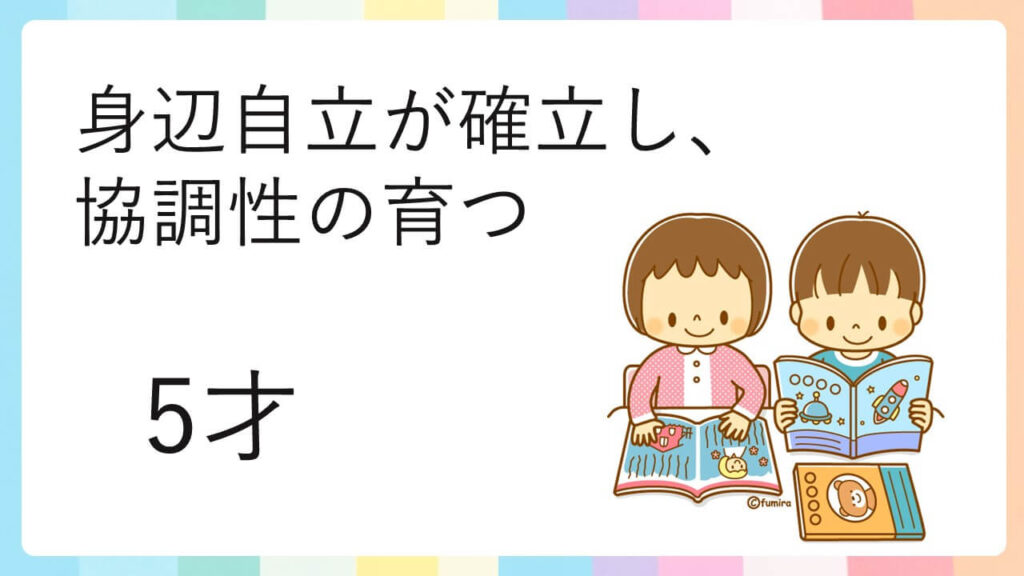
運動機能がますます伸び、よろこんで運動遊びをしたり、友達といっしょに活発に遊んだりする時期。
食事・トイレ・衣類の着脱などの基本的な生活習慣が身につき、ご両親の負担も減ってきているのではないでしょうか。
「家庭」と「幼稚園・保育園」という2つの世界のほかに、「友達同士」で3つめの世界を作ります。
その結果、ケンカを子どもたちだけで解決したり、異なる考えを認めたり、社会生活に必要な基本的な力を身につけていきます。
そんな5才のお子さんの「育ち」と「おうちでできる関わり」について、以下の内容について解説します。
- 全身の運動
- 指先の巧緻性
- ことば
- 概念の形成
- 衣類の着脱
1つずつみていきましょう。
5才の「全身の運動」


5才は運動能力がグンッと成長して、「足が地面から離れた」ところで身体をさまざまにコントロールできるようになります。
運動をする場所は?
この時期になると家の中ではなく、公園やお庭などで楽しむ遊びを入れていきましょう。



当ブログのコンセプトは「おうちで」だけど、公園にでかけよう。
鉄棒
まずは鉄棒に「ぶらさがり」ます。これが基本。
ツイスト
ぶら下がったまま身体をひねります。
自転車こぎ
ぶら下がったまま自転車のペダルをこぐイメージで両足を動かします。
高い鉄棒がある場合はご両親と一緒にやってみましょう。



子どもの方が長時間できることも…
コウモリのポーズ
ぶらさがった状態から両足をかけます。



ケガをしないように、すぐに身体を支えられる位置で見守ってね。
登り棒・ジャングルジム
公園にある遊具を子どもなりに楽しんで遊ぶだけで、子どもに合った全身運動になります。
特に「よじ登る」という動作が効果的です。
縄跳び
この時期は、自分で縄を回して飛ぶよりも、大繩飛びのようにご両親が縄を回してあげる運動が合っているお子さんが多いです。
家に長縄があるようなら以下の遊びを試してみるのがよいでしょう。
- 姿勢をかがめて地面に両手をついて飛ぶ
- 片足を上げたまま飛ぶ
- 「さようなら」と言って回っている大繩から出る
缶ぽっくり
昔からある定番の遊び。
くだものの缶詰めなど、少し大きめの空き缶に紐を通し、その上に乗って歩きます。
上手になったら線の上を歩いたり、ちょっとした段差を上がったり。
バランス感覚が養われますよ。
5才の「指先の巧緻性」


大きな運動の次は「指先の巧緻性」について解説します。
指先の巧緻性
指先の器用さのこと。鉛筆やハサミの使用に関係する動作。その他、衣類の着脱、手洗い、歯磨きなどの生活に必要な活動の土台となる。
目、手、身体が協応的に動いて、複雑な動きを連続的に行えるようになる時期です。
そんな時期の「指先の運動」が高まる関わりを紹介しますね。
姿勢も意識して
椅子に座って行う活動が多いですが、意外と大切なのが「姿勢」。
集中力にも影響します。
ひらがな練習
5才になれば、おうちでの「ひらがな練習」に取り組んでいるご家庭も多いのではないでしょうか。
お子さんの習得状況に応じて
- 線引き
- 迷路
- なぞり書き
- マスの中に書く
の取り組みをします。
「ひらがな練習」はすぐに成果はでないものの、練習することによって少しずつ上手になっていきます。
書けたかどうかよりも、頑張った「過程」を褒めて取り組んでくださいね。
お絵描き
運筆能力も向上し、5才では描画能力も向上していきます。
後ろ姿や横向きの人を描いたり、紙のバランスを考えて描いたりするお子さんもいます。
お手本を見て、マネして描くこともできる子もいるでしょう。
走る人を描く場合に「曲がったヒザ」の描き方見せるなど、お手本の提示も効果的です。
折り紙
幼稚園や保育園で教えてもらった折り方を、家でも得意そうに披露してくれるお子さんもいると思います。
5才のお子さんでは、難しすぎない折り紙の折り方を教えてあげましょう。
手順が少なく、複雑な操作の必要のないものがいいですね。
- ハート
- 紙飛行機
- チューリップ
などの定番のものがおススメです。
色々なものを作るよりも、同じものを繰り返し作ることを好むお子さんが多いです。



上手にできた満足感が高いので、同じものを作るのかな。
紐とおし
紐とおしは、紐を持ち変える必要があるので、指先の細かな運動の練習にうってつけです。



ボタンの練習にもなるよ。
「穴が開いたもの」と「紐」があればよいですが、簡単に準備できるものでは「ストローを輪切りにしたもの」の紐とおし。
女の子であれば(男のでも)「ネックレスを作ろう」と言ってご両親が作り始めれば、興味津々にやりたがります。。
5才のことば


日常的な会話はスムーズになり、会話のキャッチボールもできるようになる時期です。
質問に対する返答も上手になります。
昨日のこと、明日の予定をお話ししてくれることもあるでしょう。
とはいえ、筋道を立てたお話しでは「あいまい」な部分もあり、ご両親は推測しながら聞く必要があります。
6才に向けて、時間的な連続性、出来事のつながりをもった「筋道を立てたお話し」ができるように関わっていきましょう。
そのための、おうちでできる関りを紹介します。
絵本
5才にもなると集中力がつき、今までよりも長いお話を最後まで聞けるようになってきているのではないでしょうか。
絵本自体が「筋道」ができた構成になっています。
絵本選びでは、子どもが読みたいものを選んであげることを優先しつつも
- 心の動きがある絵本
- 世界観のある絵本
- 定番の絵本
なども取り入れてみましょう。
子どもが読めるような「ひらがな」で書かれている絵本を選び、お子さんに読んでもらってもよいですね。
絵日記
絵日記は「語い」を増やす効果がかなり大きいです。
ポイント
絵と文字を書くのはご両親です。
一緒にでかけた場所を振り返りながら、ご両親が絵を描きます。
お子さんとの会話を楽しみつつ、
- その時に見たもの
- その時に感じたこと
- その時に考えたこと
などを引き出しながら絵を描いていきます。
また、
「きょうはこうえんにいったよ。おおきなかまきりがいてびっくりしたよ。」
などとご両親が「ひらがな」で書いて、読んでもらうことで説明上手にもなります。
しりとり
言葉の仕組みに気づくことで「しりとり」を楽しめるようになります。
言葉の「音の構成」を、楽しみながら理解できる優れた遊びです。
音の構成
言葉の音の構成を理解することは、「音韻意識」と呼ばれ「ひらがなの読み書き」にとても大切な力です。
カルタ
カルタは「文字への興味」を深めつつ、子どもが熱中できる遊びです。
ひらがなをスムーズに読むのは、まだ難しいお子さんが多いと思いますので、読み札はご両親が読んであげましょう。
始めは「絵」を見て探しますが、それで大丈夫です。
繰り返しているうちに少しずつ、「ひらがな」を見て探せるようになっていくお子さんが多いですよ。
なぞなぞ
なぞなぞは、「なぜその答えになるか」がわかるために、理解力が求められます。
年齢別の「なぞなぞの本」もあるので利用してみるのがよいでしょう。
- 「冷たくて甘い、イスはな~んだ?」
- 「足が1本、目が3つの「き」はな~んだ?」
5才の「概念の形成」


「概念の形成」というと少し難しいですね。
「モノの特徴がわかる力」というニュアンスです。
「リンゴ、みかん、はさみ」の3つのうち「はさみ」が仲間はずれでだとわかるのは、「くだもの」という概念があるからです。
概念があると「共通認識」ができるので、コミュニケ―ションが効率的になります。
30cmのリンゴを見て「すごい!」で伝わるのは、一般的にリンゴは10cmくらいという「共通認識」があるからです。
「ことばの発達」にも影響する、「概念」の形成を育む関わりを紹介します。



ここでは「数」も概念に含めて説明するよ。
5才の「概念形成」をサクッと解説
5才では科学的な好奇心が高まる時期です。
例えば
- 影絵遊び
- 磁石
- 紙飛行機
- コマなど
また、「赤・青・黄色」「グー・チョキ・パー」など3つで1セットのモノに興味を持ったり、「左右」についてもわかり始めたりします。
さらに、「時間」についての理解も進みます。



時間について何となくわかるけど、時計を読むのはまだ難しいよ。
数が同じ
見た目や配置が違っても、「同じ数だ」と分かるように促します。
例えば、
- 「ラムネ」と「アメ」を5個ずつお皿に分けるお手伝いをしてもらう。
- 5個のお皿に、5個のドーナツを1つずつのせるお手伝いをしてもらう
など。



「数」はお菓子を使ったお手伝いをしてもらうと理解しやすい!
連想ゲーム
連想ゲームは競争するとお子さんが夢中になります。
例えば
- 赤いもの
- 冷たいもの
- 三角のもの
- 3文字のものなど
色・温度・形・文字数などのテーマを挙げて行います。



色々な「概念」を身につけることができるよ。
浮かぶもの沈むもの
木と石を使って「浮かぶもの」と「沈むもの」を予想させて、実際に実験してみます。
浮かぶ理由、沈む理由などを一緒に考えます。
木と石以外にも色々なもので実験をしましょう。
おもしろい実験は「野菜」。
地面の上に育つ野菜は浮いて、地面の中で育つ野菜は沈むという特徴がありますよ。



科学的な好奇心が育つ5才にちょうどいい取り組みです。
30まで言う
30個のものを数えるのではなく、まずは30まで言えることが目標です。
お風呂で
「30まで数えたら出よう」。
と言って一緒に数えます。
毎日繰り返すことで覚えていきます。
時間を意識しよう
はじめは「短い針」に注目です。
- 「短い針が3のところにきたらおやつにしよう」
- 「短い針と長い針が12のところで重なったらお昼ごはんにしよう」
などと言葉かけして、生活と時間を結びつけるように関わります。
5才の「衣類の着脱」
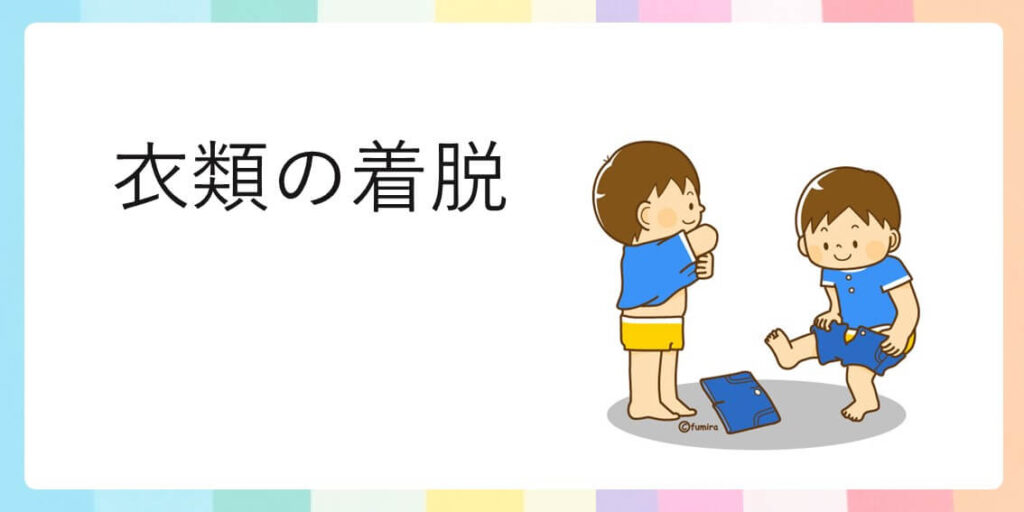
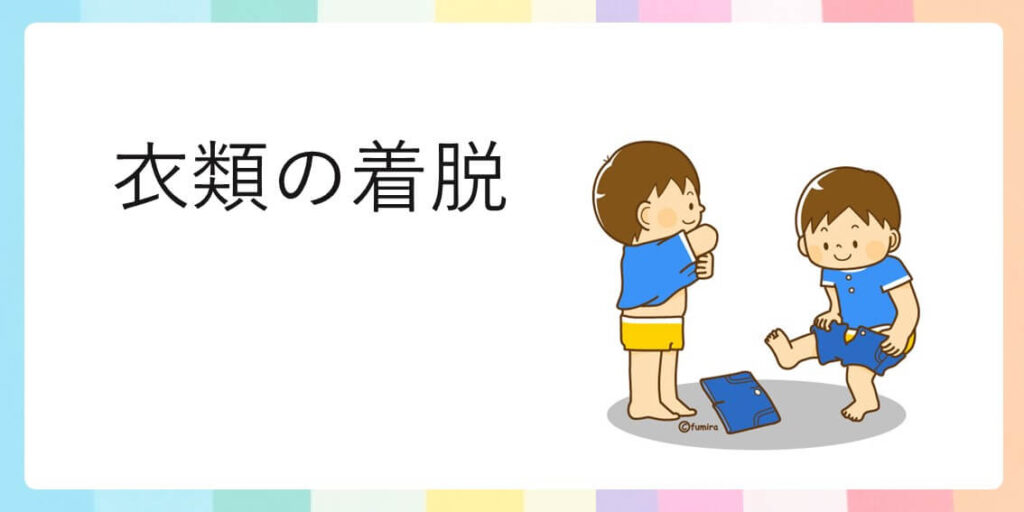
多くの服を自分で脱ぎ着できるようになります。
また、朝の着替え・お風呂後のパジャマの着衣など、生活の中で脱ぎ着のタイミングについても理解しスムーズにできるようになります。
この時期では、運動の時は伸縮性のある服、暑い日は薄着にするなど、状況に合わせて服を選択できるように言葉かけしてみましょう。
以下に5才台でできる「衣類の着脱」を挙げました。
5才台の「衣類の着脱」
- 前開きの上着を片腕ずつ通して着る
- ファスナーを自分で閉める
- 気温に合わせて自分で上着を着たり、脱いだりする
- オシャレを楽しむ
- 脱いだ服をたたみ、決められた場所にしまう
- 紐が結べる
毎日のお着替えで、自立の原動力である「やる気」を引き出してあげましょう。
まとめ
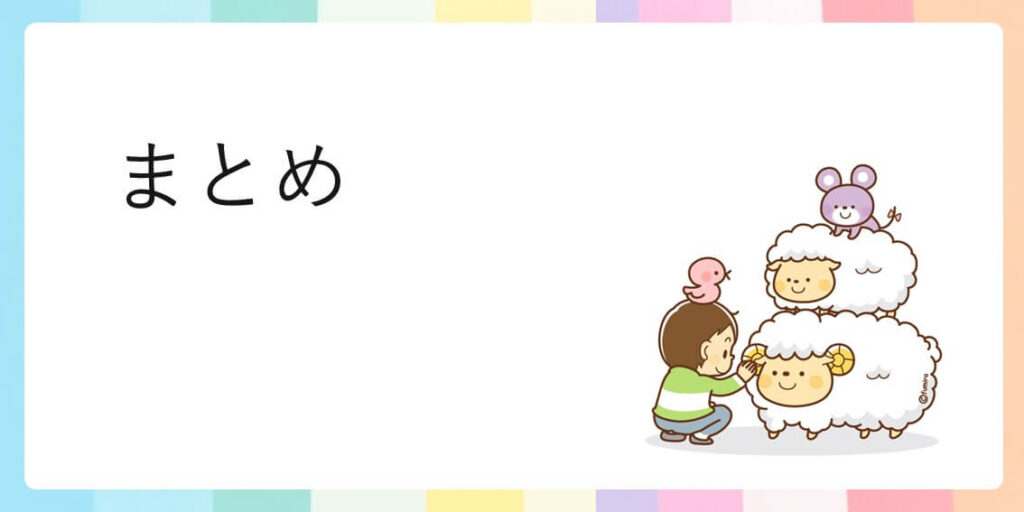
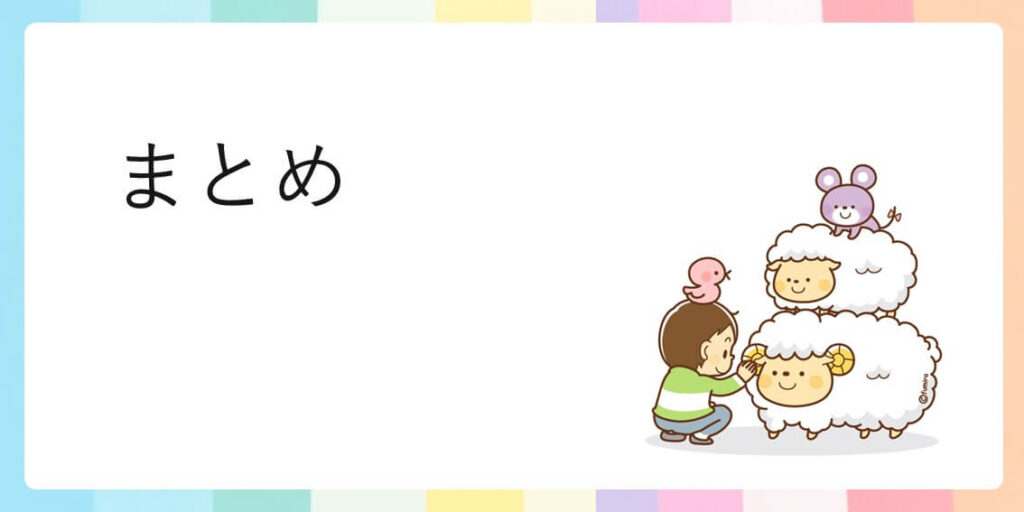
5歳のお子さんの学びと、家で取り組める関わりについて紹介しました。
おうちでできる取り組みの参考にしてくださいね。



最後までお読みいただきありがとうございました。



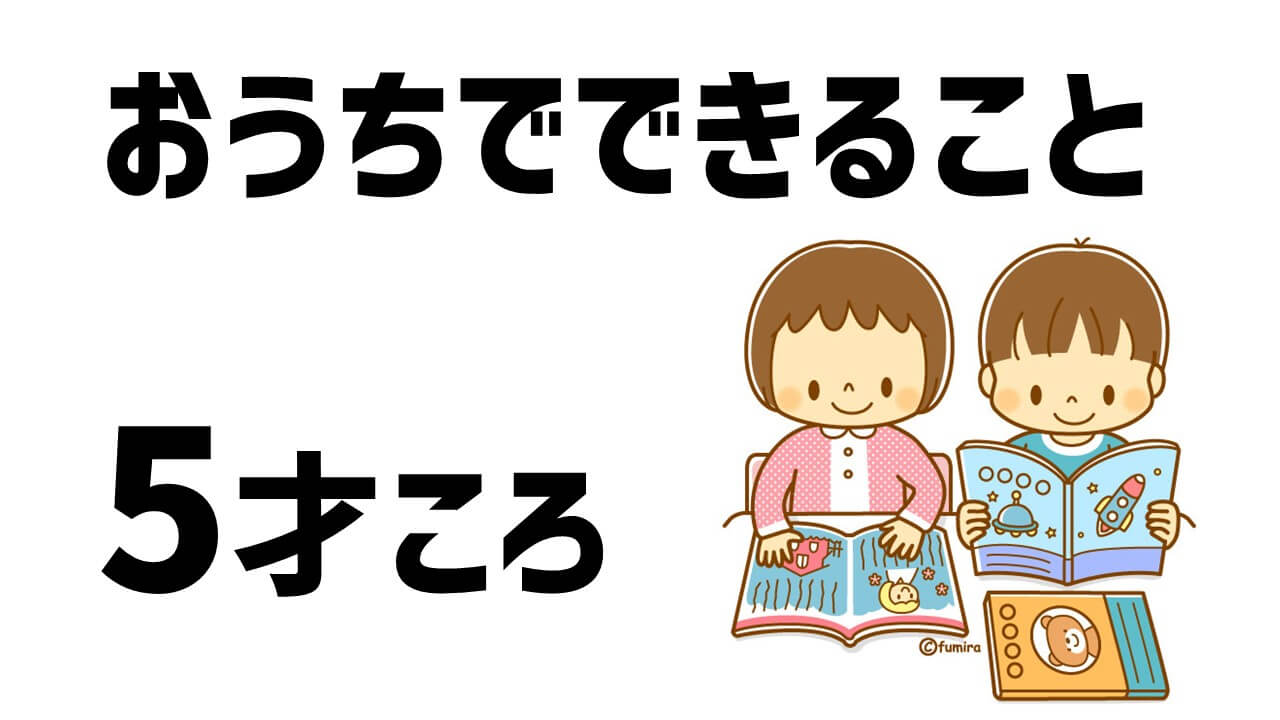
コメント