こんにちは、「くろねこ」です。
「言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)」という職業をご存じでしょうか?
まだ一般的にはあまり知られていませんが、医療・教育・福祉の分野で幅広く活躍する“ことばと聞こえの専門家”です。
このページでは、言語聴覚士とはどんな資格なのか、そして子どもの発達を支える場面でどのような役割を担っているのかを、わかりやすく紹介します。
言語聴覚士の基本的な役割
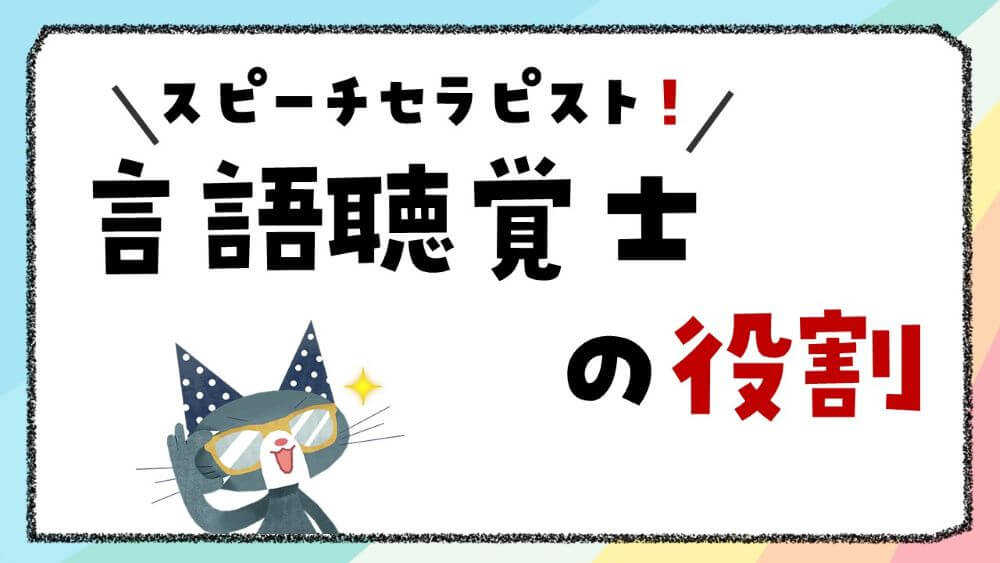
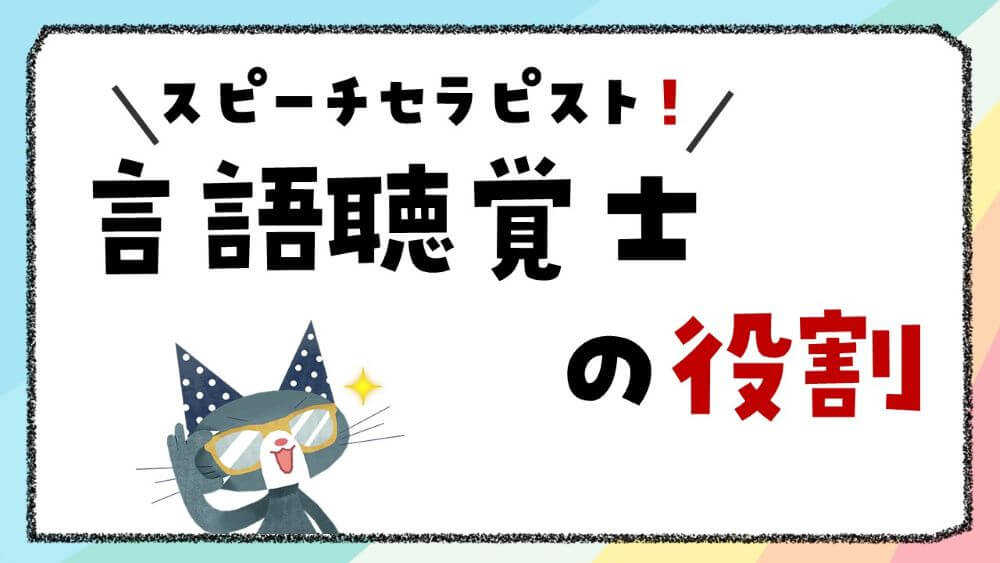
ことば・聞こえ・飲み込みを支える専門職
言語聴覚士は、「話す」「聞く」「読む」「書く」など、ことばを使ったコミュニケーションの問題や、食べ物をうまく飲み込めない(嚥下障害)といった問題に対して支援を行う専門職です。
医療だけでなく、教育・福祉の分野でも活動しており、乳幼児から高齢者まで幅広い世代を対象にしています。
リハビリ3職種のひとつ
言語聴覚士は、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)と並ぶリハビリテーションの専門職のひとつです。
身体の回復を支えるPT・OTに対し、言語聴覚士は「ことば」「聞こえ」「食べること」を通して生活の質を支える役割を担っています。
子ども分野での言語聴覚士の仕事
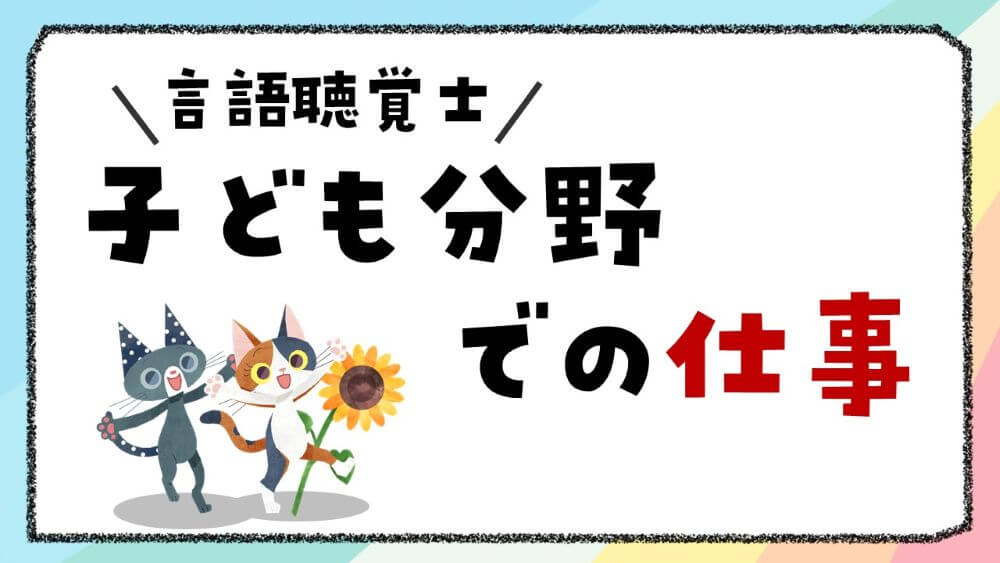
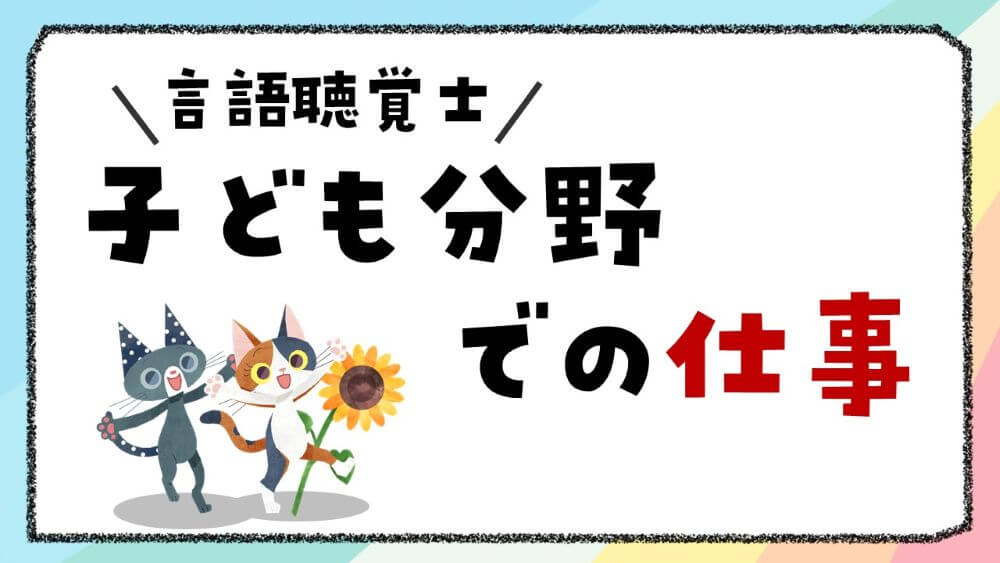
子どもの「ことば」と「発達」を支援する
子どもの分野では、ことばや発音、聞こえ、コミュニケーションに関する困りごとに対して、検査・訓練・保護者支援などを行います。
- ことばの発達がゆっくり
- 発音がはっきりしない
- 吃音(ことばがつまる)がある
- 聴覚障害がある
- 読み書きに苦手さがある
- 食べ物の飲み込みにくさがある
子ども一人ひとりの発達段階に合わせて、ことばや学びの力を伸ばすサポートを行っています。
家庭や園・学校との連携
言語聴覚士の仕事は、訓練室の中だけではありません。
保育園・幼稚園・学校の先生や、医師・心理士・保護者と協力しながら、子どもが過ごす環境全体を整えることも大切な役割です。
「家庭でどんな関わりができるか」「園ではどう支援すればいいか」など、身近な生活場面に合わせた助言も行っています。
資格としての専門性と信頼性
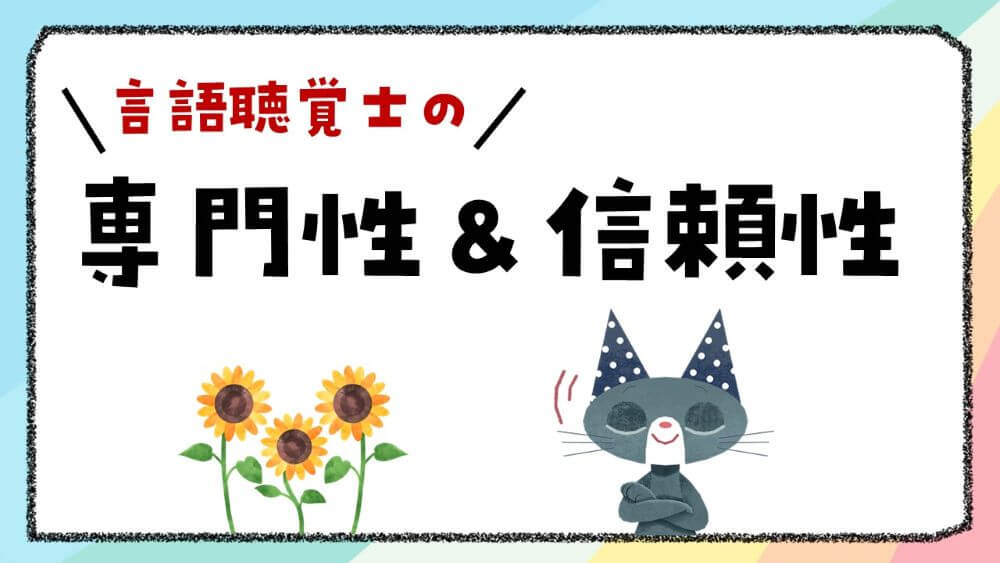
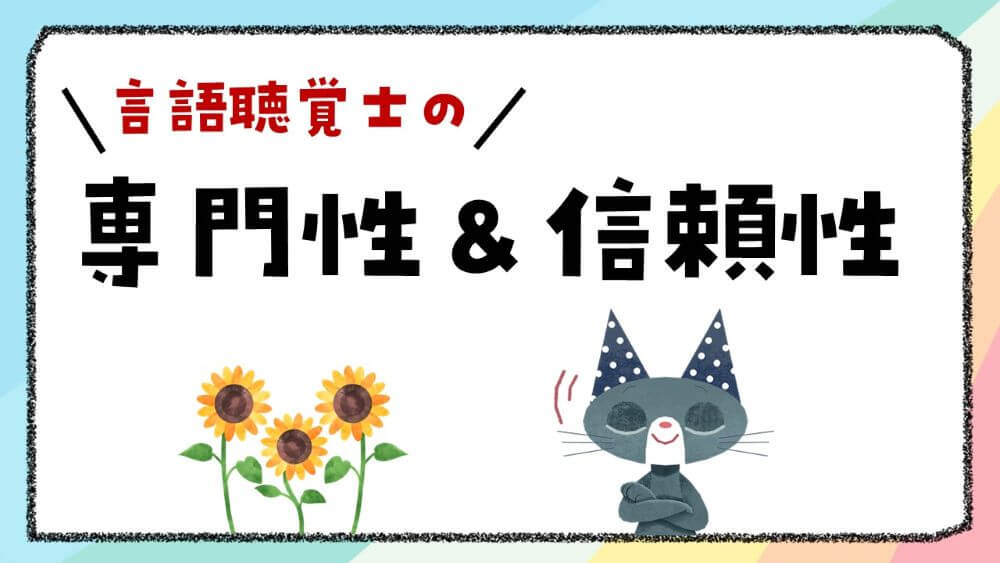
国家資格としての学びと試験
言語聴覚士は、国家資格をもつリハビリテーション専門職です。
大学や専門学校で定められたカリキュラムを修了し、国家試験に合格することで資格を取得します。
学ぶ内容は幅広く、解剖学・心理学・言語発達・聴覚・発音・嚥下など、ことばや発達に関わる知識と技術を総合的に身につけます。
医療・教育の現場での信頼
言語聴覚士は、病院やリハビリ施設だけでなく、特別支援学校や発達支援センターなどでも活躍しています。
チーム医療や多職種連携の中で、ことば・聞こえ・発達に関する専門的な立場から子どもを支えています。
『黒猫と三毛猫』では
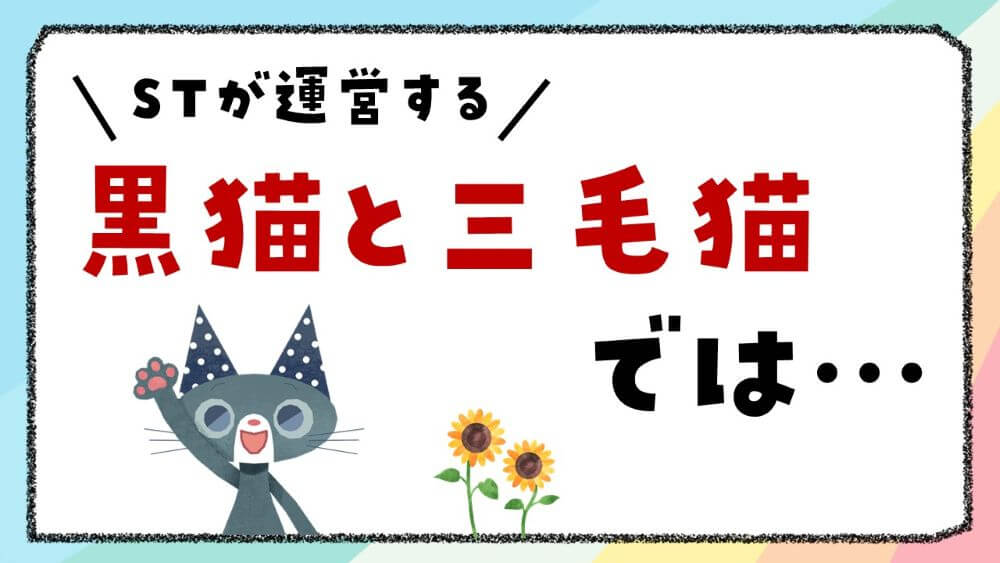
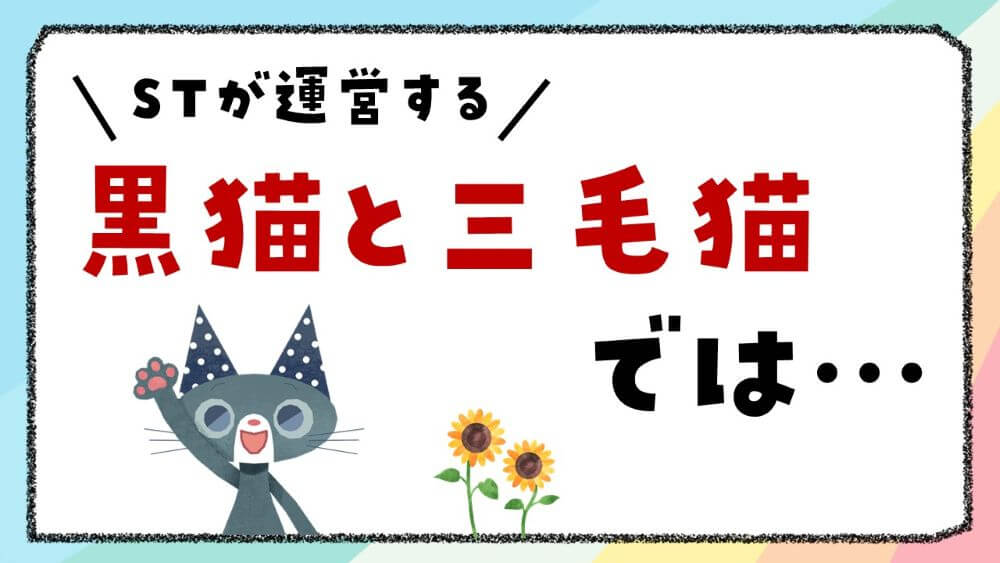
このサイト『黒猫と三毛猫』は、子ども分野を専門とする言語聴覚士が運営しています。
言語聴覚士として日々の支援を通して感じた「こんな教材があったらいいな」というプリントを制作・公開しています。
このサイトでお子さんの「ことば」と「考える力」を伸ばすお手伝いができれば嬉しいです。



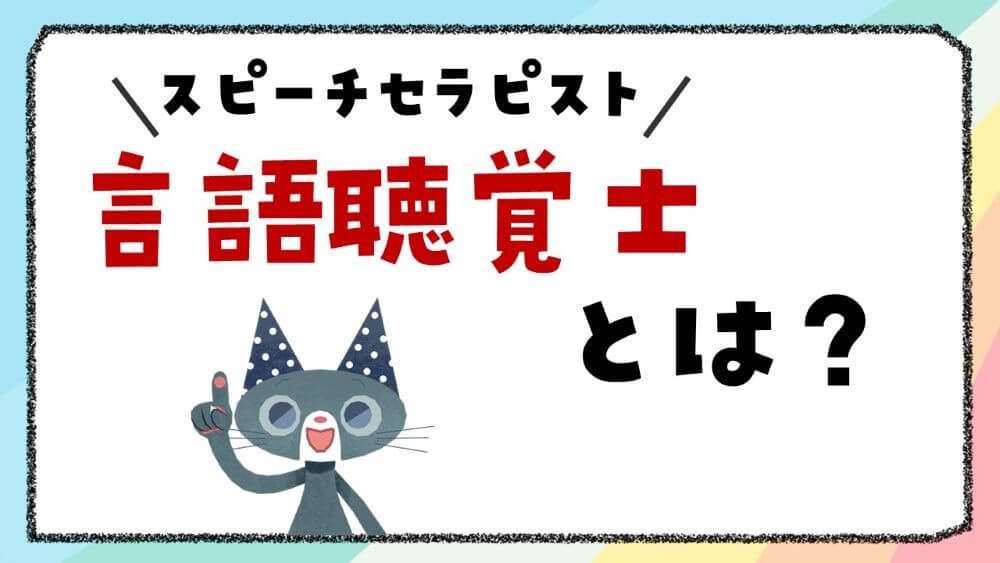
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 国家資格:言語聴覚士(ST)免許保有 […]
[…] 国家資格:言語聴覚士(ST)免許保有 […]